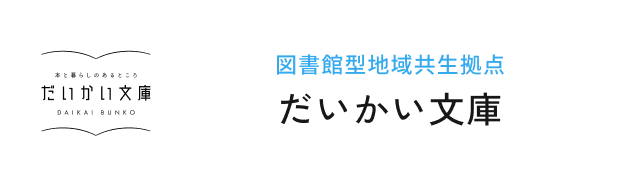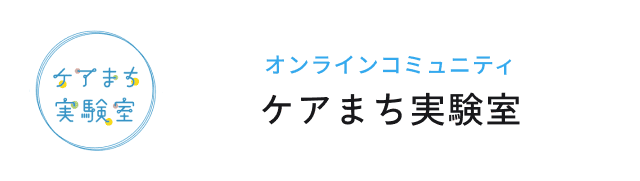暮らしの中にケアを編み直す、ケアと暮らしの編集社。孤独が自己責任化する社会で、気づいたら孤独が解消され、つながりが生まれているような予防的な処方として「暮らしの中にケアの拠点を作る活動」と「全国にケアするまちを広げる活動」の2軸に取り組みます。
その活動を支えるのは、現場にいるスタッフだけではありません。遠方にいながらも活動に共感し、継続寄付という形で応援をしていただいるケアくらメイトの存在が欠かせません。
今回お話を伺ったのは、理学療法士としてまちづくりに携わる橋本康太さん。
「近くにいれば関わりたいけれど、それが難しいからこそ、寄付という形で支えたい」
そう語る橋本さんが ケアと暮らしの編集社の活動に共感し、継続寄付を決めた理由とは? 活動への期待や、寄付者としての思いについて伺いました。
ーーー本日はお時間をいただいてありがとうございます!まず、継続寄付を始める前に、関心のあった社会課題や活動のテーマを伺いたいと思います。
橋本さん
もともと「場作り」に関心がありました。一つの建物が単一の機能を持つのではなく、多面的な関わりを持てる空間にすることに興味があります。特に、地域の人々が自然と交流できる場が地域の中にあることが重要だと思っています。
ーーーケアと暮らしの編集社を知ったきっかけは何でしたか?
橋本さん
代表理事の守本さんをSNSでフォローしていて、そこで知りました。守本さんの作るまちづくりの仕掛け方や設計に興味を持っていて、色々と学ばせてもらっています。特にいいなと思っているのが守本さんの考え方で、ただ場所を提供するだけでなく、場作りにおいて、その地域の文化的な背景や特性を活かしている点が魅力的でした。
ーーーありがとうございます。特に、活動の中で共感したポイントはありますか?
橋本さん
だいかい文庫のような複合的な施設の取り組みには共感します。特に、プロジェクトの見せ方やネーミング、アクションの仕方に興味を持っています。一般的に「居場所づくり」と言うと受け身的なものになりがちですが、だいかい文庫は積極的にコミュニティを作り出している点が素晴らしいなと思っています。
ーーー継続寄付を申し込んだ決め手は何でしたか?
橋本さん
近くに住んでいれば直接関わりたいですが、物理的に難しいので、せめて寄付という形で応援したいと思いました。利益を生む事業ではないけれど、価値のある活動なので継続してもらいたいという気持ちがあります。自分が関われなくても、寄付による継続的な応援があれば活動が広がるはずだと思いました。
ーーー毎月の継続寄付の金額はどのように決めましたか?
橋本さん
完全に自分の財布事情です。毎月1000円だと1年で1万2000円かかる、といった計算をして決めました。ただ、自分にとって負担にならない範囲で寄付することが重要だと考えています。応援を続けることが目的なので、無理のない範囲で行うのがいいと思っています。
ーーー継続寄付を申し込む前に迷った点はありますか?
橋本さん
いいえ、すでに寄付することを決めていたので、迷いはありませんでした。むしろ、応援する方法として何が最適かを考えました。直接のボランティア活動も考えたことがありましたが、地理や時間的な制約もあるため、寄付という形を選びました。
ーーー今後のケアと暮らしの編集社に期待することがあれば教えてください!
橋本さん
「形にならないものを形にする」という動きに共感しています。それが模倣可能な仕組みになれば、他の地域でも活用できると思うので、今後もその姿勢を続けてほしいですね。また、他の地域の活動とも連携しながら、新しい枠組みを作っていけると面白いなと思います。
ーーー貴重なお話をありがとうございました!
ケアをまちに編み込む仲間として、ともに歩みませんか?
ケアと暮らしの編集社では、毎月のご寄付で活動を応援する継続寄付会員を募集しています。
弊社の活動は制度の狭間に位置しているため、行政の事業や制度事業ではなく、自主事業として行っています。そのため、継続的な活動運営や発展はご寄付を収入にしています。
また、私たちは継続寄付会員のみなさまを「ケアくらメイト」とお呼びしています。単に寄付する・されるの関係性だけではなく、ケアの輪を広げていく仲間としてともに歩んでいただきたいと思っています。
継続寄付は、毎月500円から始めていただけます。ぜひご検討ください。
記事執筆者

恒本茉奈実(ファンドレイジング部)
1998年生まれ、岐阜県大垣市出身。地域での多文化共生の取り組みを通じて、社会課題の解決を目指す事業に関心を持つ。新卒から約3年間、NPOなど非営利団体向けのITサービスを提供する企業でディレクターとして従事。その後、地域での実践の場で働きたいという思いから2024年9月よりケアくらに参画。